
ブレーヴォス
『黒と白の館』に来て以来、毎日床の掃除を続けていたアリアは、ジャクエン(の顔をした男)に「弟子にしてほしい。”顔のない男”になりたい。そのために来た」と訴える。
「ヴァラー・ドヘリス(すべての者は仕えねばならぬ)。”顔のない男”は特に」と答えたジェクエンに「仕えたい」と申し出るアリア。しかしジャクエンは「我々が仕えるのは”数多の顔の神”だが、娘(アリアのこと)は自分に仕えている。まず自分を捨てろ」と話す。
アリアは館にあるさまざまな石像を目で追いながら教えを請う。
「”数多の顔の神”はどれなの?ここには異客(まれびと)も溺神(できしん)もいて、ウィアウッドの顔さえある」
「神は一柱だけ。知っているはずだろう。名前も、贈り物も」
ジャクエンは背を向けて去り、代わって担架を持った2人の男が入ってきた。彼らは床に横たわって息絶えている男を何も言わずに扉の向こうへ運び去っていった。
「どこへ運ぶの?」
近くにいる娘に聞くが、彼女もまた口を開くことなく、別の扉の向こうへ消えた。
「あなたは誰?」
石で作られたベッドが並ぶ部屋に入ってきた娘がアリアに訊いた。
「価値を知らないもらい物の貨幣を持って、ここへ来た。誰なの?」
「誰でもない」
アリアが答えると娘は彼女の腕をムチのようなものでいきなり打った。
「悲しい嘘ね。誰なの」
「言ったでしょ・・・・・」
もう一発。さらにもう一発。
「誰なの?」
ベットに座り込んだアリアを見下ろして娘は訊く。
「誰なの?」
「今教えてやる・・・!」
アリアはシーツをめくって、隠しておいた針(ニードル)をつかもうとした。その瞬間――。
「何をしている」
ジャクエンが入ってきた。
「ただの遊び。”顔のないゲーム”よ」
笑みを浮かべた娘にジェクエンは「まだ早すぎる」といい、娘も「そのようね」と答えた。
「早くはない!」
アリアは立ち上がり、”顔のない男”にだってなれると主張した。
しかしジャクエンは彼女の針(ニードル)を見て言った。
「それはアリア・スタークの剣だろう?その服も、盗んだ金もそうだ。それで、誰でもない者にどうしてなれるのだ?アリア・スタークの物だらけなのに」

アリアはその娘と同じ服に着替え、アリア・スタークの持ち物を桟橋から海に棄てた。しかし針(ニードル)だけは棄てることができず、海岸の石をどけてその間に隠した。
そしてまた掃除を続けていると、老人の遺体が担架で運ばれてきて、扉の向こうへ消えた。するとジェクエンが肩に手を置き、ついて来なさい、と目で語りかけた。
扉を抜けると地下へ続く長い石段があり、その先の小さな部屋に先ほど運ばれてきた老人の遺体が安置されていた。そこにはあの娘がいて「服を脱がすのを手伝って」と目で合図した。
アリアは黙って服を脱がし、桶に張った湯で布巾を湿らせ、遺体を拭いた。
「拭いたあとはどうするの?」
その問いに娘は答えなかった。
『数多の顔を持つ神』の背景
彼が何者だったのかはわからない(自身も奴隷だったという説もあれば、永世領の領主の息子だったという説も、奴隷を使う側の親方だったという説もある)が“顔のない男(フェイスレス・メン)”は鉱山を歩き、奴隷たちの祈りの言葉を耳にした。奴隷たちは百もの言葉でそれぞれの神に祈りを捧げていたが、その内容は同一だった。誰もが解放と苦痛の終焉を願っていたのだ。
しかし、奴隷たちの苦行は続き、“顔のない男(フェイスレス・メン)”は「この者たちの神には耳がないのか?」と悲しんだという。そしてある晩、唐突に悟りが訪れた。
いかなる神にもそれぞれの道具がある。その神に仕え、その意志を地上に示す道具となる男女がいる、この奴隷たちは、百の異なる神々に祈っているが、実は百の異なる顔を持つ「ただ一柱の神」に祈っているのではないか。そして自分こそが、その神の道具ではないのか――。
悟りを開いた“顔のない男(フェイスレス・メン)”は、奴隷の中で最も追い詰められていた者、誰よりも強くこの地獄からの解放を祈っていた男を選び、死という贈り物を授けてその願いを叶えてやったのだ。その後“顔のない男(フェイスレス・メン)”は奴隷をこき使ってきた永世領の貴族にも、贈り物を授けるようになったという…・・。
その末裔が、ジェクエン・フ=ガーというわけですね。

キングズ・ランディング

トメン・バラシオンは、民衆から絶大な支持を得ているマージェリー・タイレルと結婚した。彼女が寝室に忍び込んできた時から待ち望んでいた行為を「あっという間」に終え、息を弾ませながら「痛くはなかった?」と気遣うトメンに、マージェリーは「今までのどの王よりもお優しい」と感激して見せる。
そして「兄が亡くなったおかげで世界一美しい女性と結婚できた」と素直に喜び、いつか船旅をしようと声を弾ませるトメンに、邪魔者――太后サーセイを遠ざける役目を与える。
「お母様はあなたを守ってくださる。子どもを守る牝の獅子ね」
「子どもだと?僕はもう大人だ」
「ええ。そして王です。でも、お母様にとっては子ども。夫君、ご長男に続いてお父上も亡くされたのだから、あなたを守りたいと思われるのも当然ね。ずっと傍に置いておきたいと思っておられるわ、きっと」
(母上から離れなくては)
鏡台でバラ色の髪をとかす美しい王妃を前に、トメンはそんなことを考えていた。
「母上には幸せでいてほしい。故郷のキャスタリー・ロックをよく懐かしんでおられるのは、戻りたいからではないのですか?」
赤の王城(レッド・キープ)を散歩している時にトメンからその言葉を聞いたサーセイは、やさしくて純粋なトメンを虜にして操っている者の元へ向かった。
マージェリーはベッドでの王とのやりとりを面白おかしく脚色して話し、テーブルを囲んだ侍女たちを笑わせていた。タイミングが悪かったと察したサーセイは「困ったことがあればいつでも言って」と、とりとめのない言葉を残して去ろうとするが、マージェリーはこの機会を逃さない。

ベッドでトメンがいかに元気で逞しいかを話し「さすがは獅子と牡鹿を合わせた方です」と褒めてまた侍女たちの笑いを誘った。そして背を向けたサーセイを呼び止めて訊いた。
「宮廷のことがよく分からないので教えてほしいのですが、これからは何とお呼びすれば?王の母君?それとも王太后?」
「・・・・・・格式を気にすることはないわ」
「いずれにせよ、王があまりにも熱心なので、すぐにおばあさまになられるかもしれませんわ」
「それはすてきなことだわ。いつでも言って。困った時は」
再び背を向けたサーセイを見送ったあと、マージェリーがいたずらっ子のような顔で振り向くと、侍女たちからひときわ大きな笑いが起こった。
(笑っておきなさい。いまのうちにね)
サーセイは胸の内でそう呟いて怒りの炎を鎮め、騎士たちを引き連れて部屋に戻った。
ベイリッシュの娼館で破廉恥きわまりない遊戯に講じていた総司祭(ハイ・セプトン)は、ランセル・ラニスターをはじめとする狂信的な使徒――雀(スパロウ)たちに取り押さえられた。
「我々が祖先から受け継いできた信仰を冒涜したな。おまえは罪人だ。罰を受けろ」
総司祭(ハイ・セプトン)は全裸でムチを打たれながら、キングズ・ランディングを引き回された。
総司祭(ハイ・セプトン)は、これを七神に対する冒涜だと言って小評議会に乗り込み、雀(スパロー)たちの指導者・雀聖下(ハイ・スパローー)を処刑するべきだと訴えた。
サーセイは蚤のたまり場で馬車を降り、雀聖下(ハイ・スパロー)の居場所を訪ねた。彼は蠅が飛び、腐臭が立ちこめる広場にいた。薄い布を纏い、裸足で得体の知れない色をしたスープの配膳を行っている。

「神々の代理人を捕らえるのは横暴よ」
ひどい臭いに耐えながらサーセイが言うと、彼はパンのかけらを配りながら答えた。
「偽善は腫れ物です。切り取るのは難しい。彼らはもっと注意して切り取るべきでした」
「総司祭(ハイ・セプトン)がわたしの元へ来たわ。彼はあなたの処刑を望んでいる」
「ご自分ではどうお考えなのですか」
「・・・・・・わたしの考えは、あなたと同じよ。総司祭(ハイ・セプトン)は身も心も腐りきって堕落しているわ。あんな者に任せていては信仰がむしばまれてしまう。だから追放して牢に閉じ込めた」
雀聖下(ハイ・スパロー)は目を見開いて振り向いた。
「信仰と王の統治は世界を支える柱。どちらも崩れてはならない。できる限りの手を尽くし、互いに守り合うべきなのよ」
赤の王城(レッド・キープ)に戻ったサーセイは、グレガー・クレゲインを実験台にして死霊魔術の研究を続けているクァイバーンの部屋を訪れ「北部のどこかにいるベイリッシュに使い鴉を飛ばしなさい」と命じ、書状を託す。
「ただちに、の意味がリトルフィンガーに間違いなく伝わるようにしておいて」
サーセイはそう言って部屋を出ていった。
ウィンターフェル城
スターク家を裏切り、自らが焼き払って廃墟にしたウィンターフェル城の復興工事が進むなか、シオン・グレイジョイは、生皮を剥がされ、吊された遺体を見て顔を背ける。リークと呼ばれている今も、かつてこの場所で罪のない子どもを殺して吊した記憶は消えていないのだ。

今でもスターク家に忠誠を誓っている北部諸侯のもとへ徴税へ行き、彼らの生皮を剥いで戻ってきたラムジーに、ルース・ボルトンは強い口調で諭す。
「他の家に結託され刃向かわれると北部は維持できない。分かっているのか?」
「ラニスター家との同盟があれば――」
「タイウィン・ラニスターとの同盟だったのだ!そして彼は死に、残されたラニスターは混乱している。彼らは北部のこの地まで兵を出したこともない。もうアテにはならんのだ」
ナイフとフォークを置いたラムジーに、ルースは続ける。
「ボルトン家は他の家との同盟によって足場をかため、力を付けてきたのだ。同盟関係をさらに強める術は、生皮を剥ぐことではなく、婚姻だ」
「・・・・・・」
「今やおまえもボルトン家の男だ。相応の妻を娶れ。幸い、北部での立場を強くするためにこれ以上ない花嫁がいる」
要塞(モウト)ケイリン

要塞(モウト)ケイリンを見下ろす丘の上で馬を下りたサンサ・スタークは、ピーター・ベイリッシュから行き先は故郷のウインターフェルだと知らされる。今、城主としてそこにいるのが兄と母を裏切ったルース・ボルトンであることを知っていたサンサは、その息子ラムジーとの結婚は絶対に嫌だと言い、「無理矢理連れていこうとするなら食事を絶って餓死してやる!」と涙を流して叫ぶ。
しかし、その悲痛な思いさえも利用するのがベイリッシュという男だった。
彼は「どうしても嫌だというのなら引き返します」と前置きした上でサンサに言った。
「あなたは今までずっと逃げてきた。暗い部屋に閉じこもり、自らの悲運を嘆き続けてきた。しかし、傍観者でいるのも、逃げるのも、もうおしまいにしましょう」
ベイリッシュは両手でサンサの頬を包むようにして撫で、涙に濡れた目に訴える。
「この世に正義などありません。だから生み出すのです。愛する家族のために、復讐を」
(ボルトンに復讐するためにラムジーと結婚しろと?)
サンサはその場を動かずに北部の上空に立ちこめている雨雲を追っていたが、やがて自ら馬に跨がり腹を蹴って促した。その背中を追いながらベイリッシュは、思惑通りに事が進んでいることに満足した。

サンサたちの動きを高台から確認し、ウィンターフェルへ向かうと確信したブライエニー・タースは、「見失うのでは」というポドリック・ペインの心配をよそに、要塞(モウト)ケイリンを大きく迂回するルートを選択し、馬を進めた。

その夜、野営地でポドリックはティリオン・ラニスターの従士になったいきさつを話し、ブライエニーは剣に生きることを決めた理由を話した。そしてブライエニーは、いつか必ずスタニス・バラシオンを倒してレンリーの敵を討つとポドリックに伝えた。
黒の城(カースル・ブラック)
冥夜の守人(ナイツ・ウオッチ)総帥となったジョン・スノウは、かつてジオー・モーモントがそうしてくれたようにオリーを専属の雑士(スチュワード)として傍に置き、スタニスとの会談に臨んだ。
ジョンは「ずっとスタークになりたかった」と胸の内を正直にさらした上で、スタニスに忠誠を誓い、ウィンターフェルの城主になるという選択肢を絶った。なぜなら彼は誓いを立てた冥夜の守人(ナイツ・ウオッチ)であり、その総帥だからだ。
「名誉を重んじて死んだ父親によく似ているな。決心したなら仕方がない」
席を立ったスタニスに、ジョンは食糧がないからできるだけ早くここを離れてほしいと頼み、スタニスは2週間以内にウィンターフェル城へ行くと告げた。
名残惜しいのか、スタニスはアリザー・ソーンを左遷して東の物見城を指揮させるべきだと進言。ジョンが「敵は近くに置くものですよ」と答えると「少なければな」と言って部屋を出ていった。

しかしダヴォス・シーワースはその場に留まり、ジョンに言った。
「陛下はおまえに一目置いている。あんな言い方しかできないが、おまえを信用している」
「失望させてしまったな」
「陛下は誰よりも七王国のためを思っている」
「自分が王であればそれでもいいが」
「陛下こそが王だ。七王国の正式な王だ」
「俺は政治とは一切関わらないと誓った」
「そうか?」
ダヴォスは扉の前に立つオリーに、冥夜の守人(ナイツ・ウオッチ)の誓いの言葉を諳んじさせた。
「・・・・・・我は暗闇に生きる剣士なり。壁の見張り人なり。人々の領土を守りゆく楯なり――」
オリーの言葉を遮ってダヴォスは続ける。
「人々の領土を守りゆく楯。それがおまえたちだろう?俺には教養はないが、この世の果ての凍える城に座っていて人々を守れるとは思えん。長靴を汚しながら泥のなかを進み、必要なことをなさなければ」
「何が言いたい?」
「ボルトンが治める限り、北部は苦しむ。俺の意見だがな」
ダヴォスは席を立ち、オリーが扉を開けた。

ジョンは守人たちを食堂に集め、ブライアンを便所の穴堀係に、アリザー・ソーンを哨士長(ファースト・レンジャー)に任命した。総帥の権限でアリザーを便所の穴堀係にすることもできたが(アリザーは覚悟していたようだ)、マンス軍との戦いで見せた勇猛果敢な姿勢とこれまでの実績を正当に評価したのだ。
そして、ジャノス・スリントには灰色の楯(グレイ・ガード)の指揮官を命じた。しかしジャノスは廃墟の復興など断ると吐き捨てた。王都の守人(シティ・ウオッチ)の指揮官だったというプライドが許さないのだ。
ジョンはこれは提案ではなく命令だといい、荷物をまとめて今すぐ灰色の楯(グレイ・ガード)へ発てと静かに告げた。それでも総帥を小僧扱いし「落とし子の命令などくそ食らえ」と吐き捨てたジャノスは、どや顔でジョンを睨みつけた。
「ジャノス公を外へ。オリー、俺の剣を」
ジャノスは外に連れ出され、首を突き出す格好でひざまずく。

「悪かった。従うよ。あんたが総帥だ。今まで申し訳なかった・・・!ずっと怖かったんだ」
(マンスにイグリット、ジオー・モーモント、グレン、クォリンが死んで、どうしておまえのような奴が生き残っているのだ)
ジョンは剣を抜き、涙を流して慈悲を求めるジャノスの首に振り下ろした。
剣を預けて顔を上げると、その先にスタニスの姿があった。彼は満足そうに頷くと、そこから離れた。
ウィンターフェル城

ウィンターフェル城に戻ってきたサンサは、妻のウォルダ、ラムジー、そして騎士たちを集めて迎えたボルトンに笑顔を見せて出迎えを感謝した。
(あなたたちに復讐するために戻ったのよ)
サンサはなつかしさを押し殺しながら部屋にへ向かった。彼女を案内した老女は「おかえりなさい、レディ・スターク。北部は覚えています」と言った。
工事が進む城内を歩くサンサの姿をテラスから見ていたラムジーは、「確かに美しい。幸せにしてやりたい」とベイリッシュに話す。
「そう願いたい。私も一緒に旅をしてさらに愛情が湧きました。もう苦しませたくない」
「傷つけません。約束します」
「ところで私はあなたのことをよく知らない。貴族でいらっしゃるのに、噂を聞きませんね」
「貴族になったのは最近です。私は落とし子でしたから」
ボルトンが上がってきて席を外すように促すと、ラムジーは「一生恩に着ます」とベイリッシュに頭を下げてその場を離れた。
「喜んでおられました」
「それは当然だろう」
「処女であることは保証します。ティリオンは床入れを行いませんでした。体を調べてみますか?」
「そんなことはしなくてもいい。大事なのは家名。それだけだ」
ボルトンとベイリッシュは人気のない方へ移動しながら話を続ける。

「このあとどうなるか覚悟はしているな?ラニスターがこの婚姻を知ったらどうするか」
「ラニスターにはもう、かつての力はありません。ジェイミーには右手がなく、トメンはまだ幼い」
「王妃は激怒するだろう」
「マージェリーはサンサと親しい。サーセイの影響力は日ごとに弱くなっています」
「しかし彼女には友人が多い。頼みを聞く者があちこちにいるようだ」
そう言ってボルトンは懐から小さく丸められた書状を出した。
「サーセイから、君への手紙だ。夜明け前に高巣城(アイリー)から使者が届けにきた。
「・・・・・・私宛の手紙なのに封が開いているのはどういうことでしょう?」
「私の立場も分かってもらいたい。夜中に太后から手紙が届けば、君を疑うのは当然だろう」
ベイリッシュはボルトンを見据えてから、文面に目を落とした。。
「君はラニスターのおかげで貴族になったはずなのに、ここへきて彼らの力を奪っている。どうしてこんな賭けに出た?」
「賭けなければ野望を果たすことはできない。あなたがロブ・スタークを刺したのも賭けでしょう。そして幸運にも賭けに勝ち、北部総督となった」
「後ろにタイウィンがいたからだ。今は誰がいる?君か?」
「高巣城(アイリー)は私のものです。以前、高巣城(アイリー)は北部の諸侯と手を組み、このウェスタロスで史上最大の王国を崩壊させました」
「ふん」
「使い鴉をお貸しください。サーセイに返事を出さねば」
「中味は読ませてもらうぞ」
ボルトンは階下へおりていった。
ヴォランティス

「いい加減、馬車から降りたい」
「こんな大きな町をあなたが歩けば、必ず賞金稼ぎたちに見つかる。どうしてそれがわからないのです?」
ヴァリスは顔をしかめて説得するが、ティリオンは「おれがこのままおかしくなってしまったらデナーリス・ターガリエンに会ったところで何もできない。おまえ以外の顔を最後にいつ見たのか、もう思い出せないほどなんだぞ」
「見つかれば、おかしくなるだけではすまないのですよ」
それでもティリオンは聞かず、フードを被って外に出た。
ティリオンとヴァリスは、顔にさまざまな目印(入れ墨)を付けられた奴隷があふれかえっている市場を歩いた。広場ではデナーリスを救世主と崇める紅の祭司が教えを説いていた。
やがて2人は女がいる酒場へ入った。
奴隷解放者デナーリスの影響はこんな店にまでおよんでいて、デナーリスと同じ髪型をして、尻のところに大きな穴を開けた青いドレスを着た女が人気を集めていた。ティリオンは、男たちの膝に乗るその女を見て、酒を呷り、ため息をついている男がいることに気づかなかった。男はジョラー・モーモントだった。


ジョラーは小便に立ったティリオンの後をつけてロープで縛り、猿ぐつわを噛ませて肩に担いで言った。
「クイーンへの手土産にするよ」
ゲーム・オブ・スローンズ 完全ガイド シーズン5『第3話/雀聖下(ハイ・スパロー)』地図と登場人物



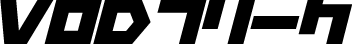




コメント